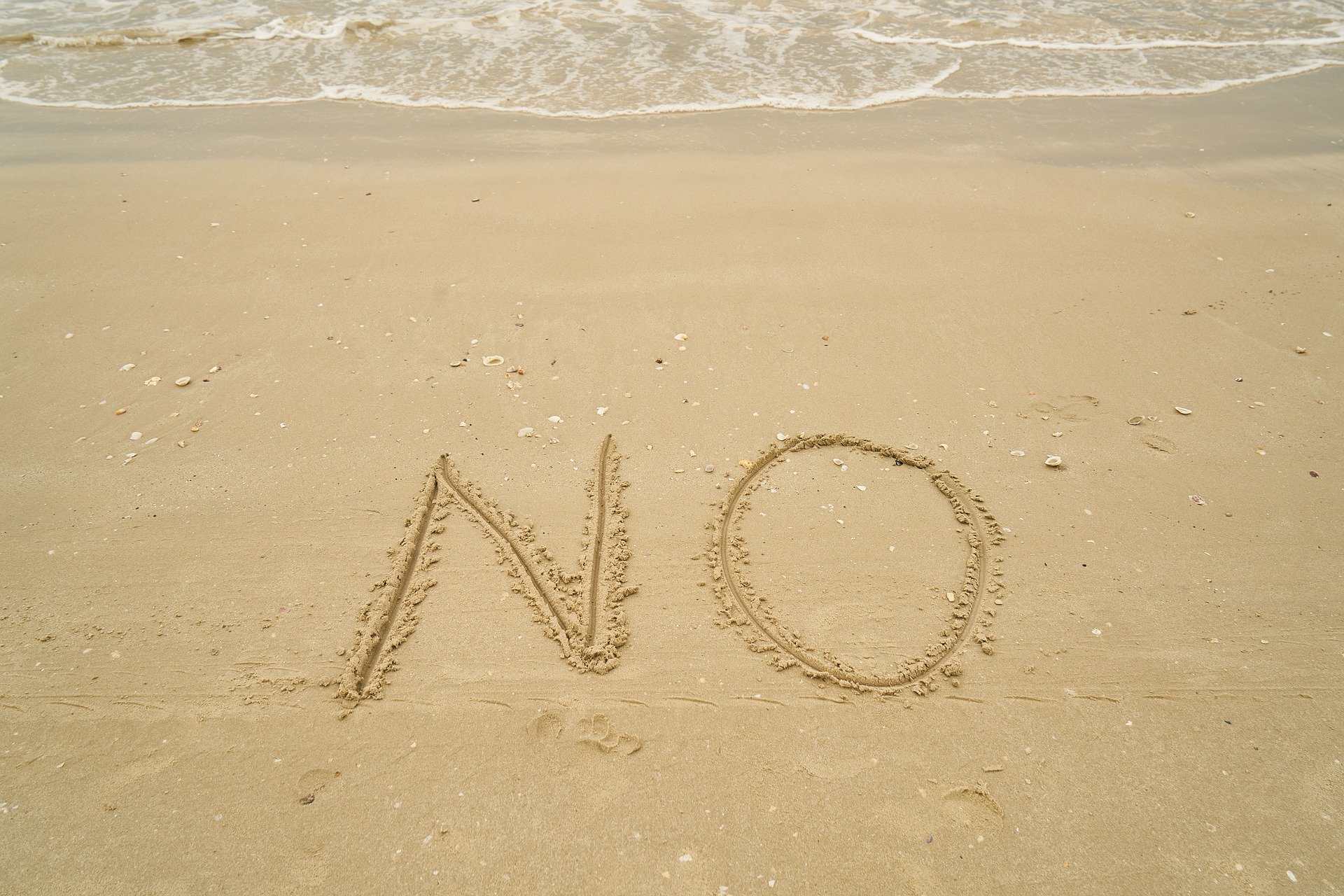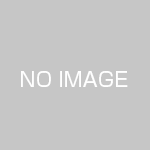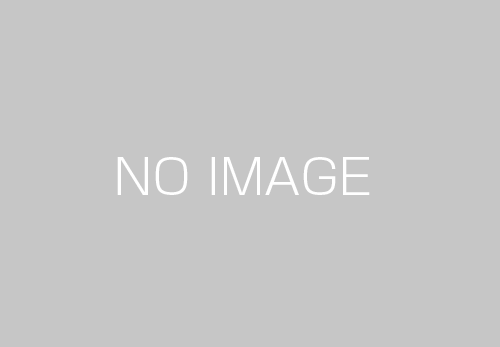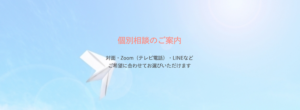発達障害・グレーゾーン
子どもの困った行動をおうちで解決!
おうち療育アドバイザー浜田悦子です。
こんにちは。
今日は、こちらのお悩みにお答えします。
◆ お悩み
布団の中や、
公共の場で静かにして欲しい時など、
大きな声で歌い、おしまいと言っても理解できていない様子。
◆ 年齢:年少
◆ 困っている悩みや行動に対しての現在の対処法
バツマークを見せて、お歌はおしまいや、
同じフレーズを口ずさみ、
〜はおしまいと合図やバツマークを見せながら言っている。
オヤツを食べさせるなど。
◆ 現在の対応についてのお子さんの様子・反応
一緒に、おしまいと言う。でもすぐにまた歌いだす。

静かにしてほしい時や
静かにしてほしい場所で
大きな声が止まらない場合、
それだけで周りの人の注目を浴びて
焦ってしまいますよね・・・
今日は、刺激と過敏の視点から解説していきます。
お子さんは 言葉の意味を、理解していますか?
まず、
” おしまい ”ということを理解しているか?
確認していく必要があると感じました。
現在の対応についてのお子さんの様子が
ーーーーーーーーー
一緒に、おしまいと言う。
でもすぐにまた歌いだす。
ーーーーーーーーー
なので、理解していない可能性があります。
ここからは、
おしまいという概念を理解していないということで話を進めます。
言葉の意味を理解していない時
” おしまい ”や” 終わり ”を
教えることって、実はちょっと難しいんですね。
終わるって、様々な場面で使われます。
子どもの世界で考えてみると、
- テレビが終わる
- 絵本が終わる
- あそびが終わる
- お風呂が終わる
- 食事が終わる
などなど、色んな場面の ” 終わる ” があります。
この、色んな場面で・・・というところがやっかいなポイントです。
” 終わる ” というパターンは、ひとつじゃないんですね。
ですので、お子さんによっては、
終わりという概念を理解してないと
どういうことなのか理解していない場合があります。
言葉の意味・概念の作り方
では、どんな風に ” 終わる ” という概念を作っていくか?
教えて行くかと言うと、
- テレビが終わたら、「テレビおしまいだね」
- 絵本を読み終わったら、「絵本おしまいだね」
このように、
その行動と「終わり」という言葉を
セットで伝えていきます。
こうすることで、
少しずつ終わりの概念ができていきます。
もし、終わりの概念を理解していても
終わり・おしまいにできない場合は、
言葉などが刺激になっている可能性があります。
刺激は注目。行動が強化される理由
困っている悩みや行動に対しての現在の対処法が
ーーーーーーーーー
バツマークを見せて、
お歌はおしまいや、
同じフレーズを口ずさみ、
〜はおしまいと合図やバツマークを見せながら言っている。
ーーーーーーーーー
とのことですが、
わたしはバツマークはオススメしません。
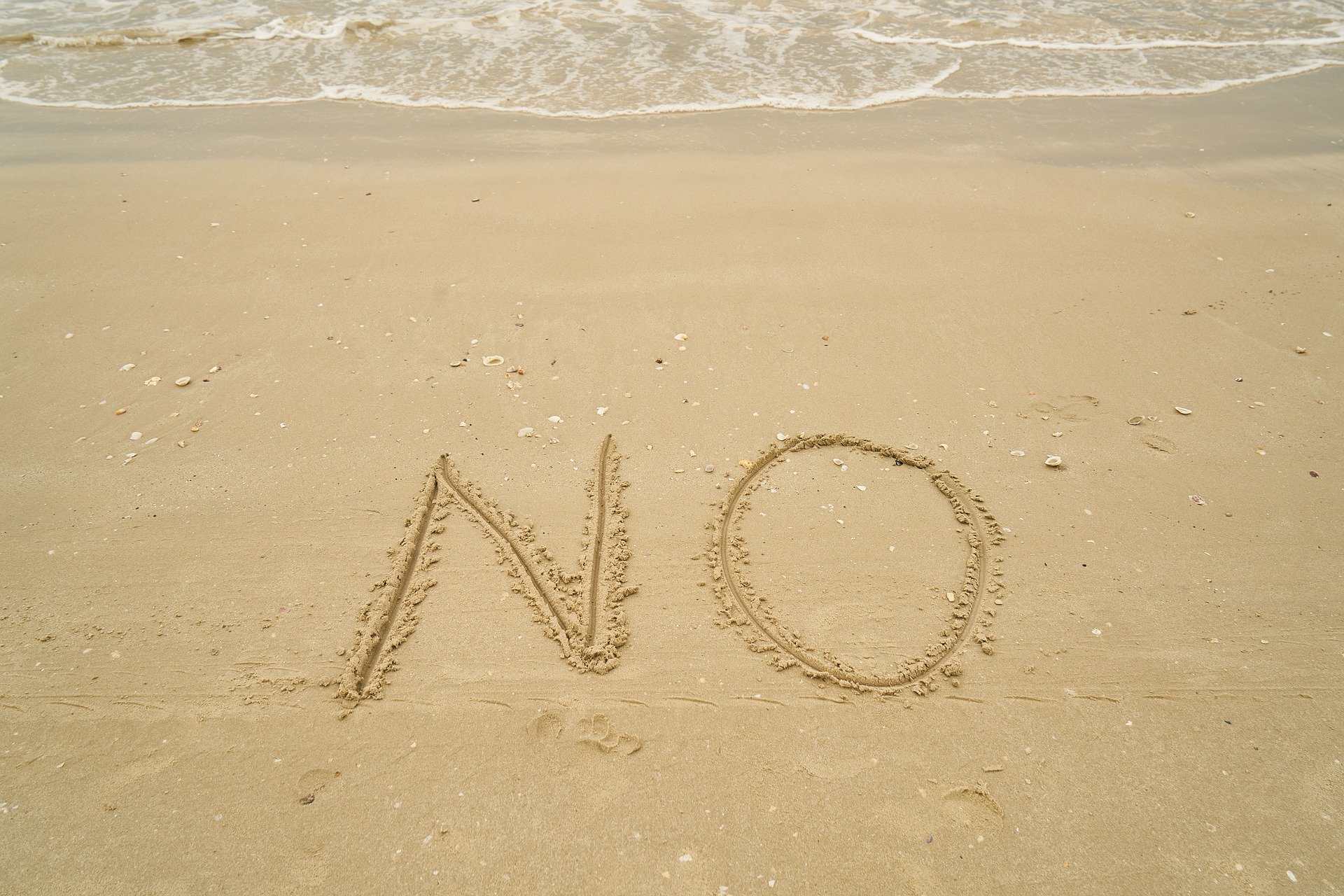
もしかしたら、
視覚的な(目に見える)指示だからと思って
取り入れているのかもしれません。
でも、バツのマークも刺激になってしまいます。
バツのマークと声も
両方が刺激となってしまいます。
刺激というのは、お子さんにとっては注目です。
” 〇〇をすると、バツのマークが出てきて、ママが反応してくれる ”
と、思っている可能性があります。
以前、発達支援センターで働いている時
こんなことがありました。
教室の中に、入ってほしくないエリアがありました。
そこにいつも入ってしまうお子さんがいて、
その子の対処法をして、バツのマークを付けたんです。
どうなったと思いますか?
次の日から、そのお子さん以外の子どもたちも
禁止エリアに入ってしまうようになったのです。
今までバツ(マーク)なんてついていなかったのに・・・
ここはなんだろう?
と、子どもたちの不適切な行動を
引き出してしまいました。
このような理由があり、
わたしは視覚支援(絵カード)や声かけでは
オススメしていないのです。
子どもたちが教えてくれたことですね^^
声の大きさの対処にも無反応
また、静かにしてほしい場所や
静かにしないといけない時に
大きな声で話すと、ママ以外にも
周りの視線や反応を得ることができますよね。
これが、お子さんにとっては
最大の注目となり、同じ行動を繰り返すことになってしまいます。
では、こんな時はどうしたらいいのでしょうか?
一番は、やはり無反応。なんですね。
ただ、無反応は外出先でやるのは
ちょっとハードルが高いかもしれません。
ぜひ、おうちの中から試してみてください。
もし、外出先で大きな声を出してしまったら
などはいかがでしょうか?
(※ ただし、飴を食べさせる行動は強化される可能性があります)
歌を歌いたいということであれば、
お子さんが知っている歌の歌詞を
クイズにしてもいいかもしれません。
同時に、お子さんが大きな声で歌を歌う時って
どんな時なのか?観察していくことをおススメします。
お子さんがその場にあった行動じゃないことをする時って、
- 暇な時
- 注目してもらいたい時
- いつも怒られている環境
であることが多いです。
その時の状況と対処法を振り返ってみてくださいね^^
聴覚過敏の可能性
さらに、大きな声で歌ったり話してしまうお子さんは
聴覚過敏の可能性があります。
聴覚過敏というのは、
聞こえているすべての音が同じ音量に聞こえる
と言われています。
ですので、自分の声も聞こえにくいので
ついつい大きな声になってしまいます。
こちらの記事も参考になさってください↓↓
声が大きくなってしまうお子さんは
” 今、自分がどんなボリュームなのか? ”
理解してないことがほとんどです。
年少さんですし、
わざと大きな声で歌ってママを困らせよう!とは
考えていないと思うんですね。
ただ、上にも書きましたが、
周りの反応を注目と捉えて
その行動が強化されている可能性はあると思います。
原因は、ひとつかもしれないし、
いくつか重なっていることもあります。
お子さんを観察しながら、
何か参考になれば幸いです。
こちらの記事も参考になさってください↓↓