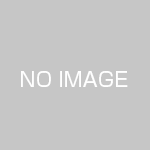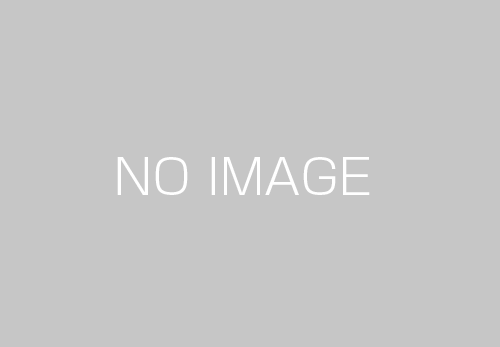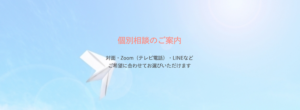発達障害・グレーゾーン
子どもの困った行動をおうちで解決!
おうち療育アドバイザー浜田悦子です。
こんにちは。
今日はこちらのお悩みにお答えします。
◆ お悩み:トイレトレーニングがすすまない
◆ 年齢:4歳3か月
◆ 困っている悩みや行動に対しての現在の対処法
自律してやるという意識が少なく、
お着替えもなのですが
トイレトレーニングが全く進まず、
以前はおしっこが出たら教えてくれたのに
教えてくれなくなり、
パンツとズボンだとかなり尿を我慢するので、
布パンツの上にオムツを履かせてトイトレしています。
トイレに座るまでがなかなかなので、
部屋におまるを置きました。
◆ 現在の対応についてのお子さんの様子・反応
おまるはお風呂上がりにだと座ってくれます。
布パンツは濡れたら気持ち悪いようだけど、
まだ替えてとは言いません。
声かけは、
「おしっこでるかも。トイレ座ってみる?」
嫌がったら座らせません。
座れたら、「たくさん座れたね」
**
お悩み、ありがとうございます。
トイレトレーニング、
お子さんもママもストレスが溜まりますよね(汗)
わたしも苦い思い出しかありません・・・
が、以下、回答です。
参考になさってください^^

正しいゴールは理解してる?
まず、
” お子さんが正しいゴールを理解しているか? ”
ということを確認してみてください。
子どもにとっては、今までは
オムツですることが当たり前でした。
でも、急に
「トイレで(おまるに)おしっこしようね!」
と言われても、
それがどういうことなのか?
理解していない場合があります。
また、現在の声かけが、
「おしっこでるかも。トイレ座ってみる?」
と、
座れたら、「たくさん座れたね」
なんですね。
これでは、お子さんは
トイレに座ることがゴールだと
認識している可能性があります。
トイレに座る ということと
おしっこをする ということが
つながっていないのです。
トイレに座るまでがなかなか・・・とありますが、
それは、元々座ることがイヤだったのか?
失敗体験があってイヤなのか?
でも変わってきます。
例えば、元々座ることがイヤなお子さんは
- トイレに座る意味を理解していなかったり
(トイレでおしっこをするということを理解していない)
- トイレの電気が暗かったり
- 嗅覚に過敏があって、色んな臭いが刺激となって
トイレに入ることがイヤだということがあります。
わたしたちは、当たり前のように
トイレに座ったらおしっこするという考えですが、
その意味と行動を、子どもが理解してない場合は
- どうしてトイレに入らないといけないの?
- トイレに入って何をするの?
- いつまで座っていなきゃいけないの?
- どうしてつまらないことを何度もやるの?

失敗体験が続いて
トイレに座ることがイヤな場合は、
一度トイレトレーニングを中断することをおススメします。
着替えもお手伝いが必要なのでしょうか?
この場合は特に、
一旦トイレトレーニングは置いといて・・・
着替えからサポートしていく。
その間に、オムツにおしっこをしたら
「おしっこでたね」と教えたり
「おしっこがでたら、ママにでたよって教えてね」
と伝えて、まずは
” それがおしっこがでたということだよ ”
” 教えてくれてありがとう ”
という意識を作っていくことが必要かもしれません。
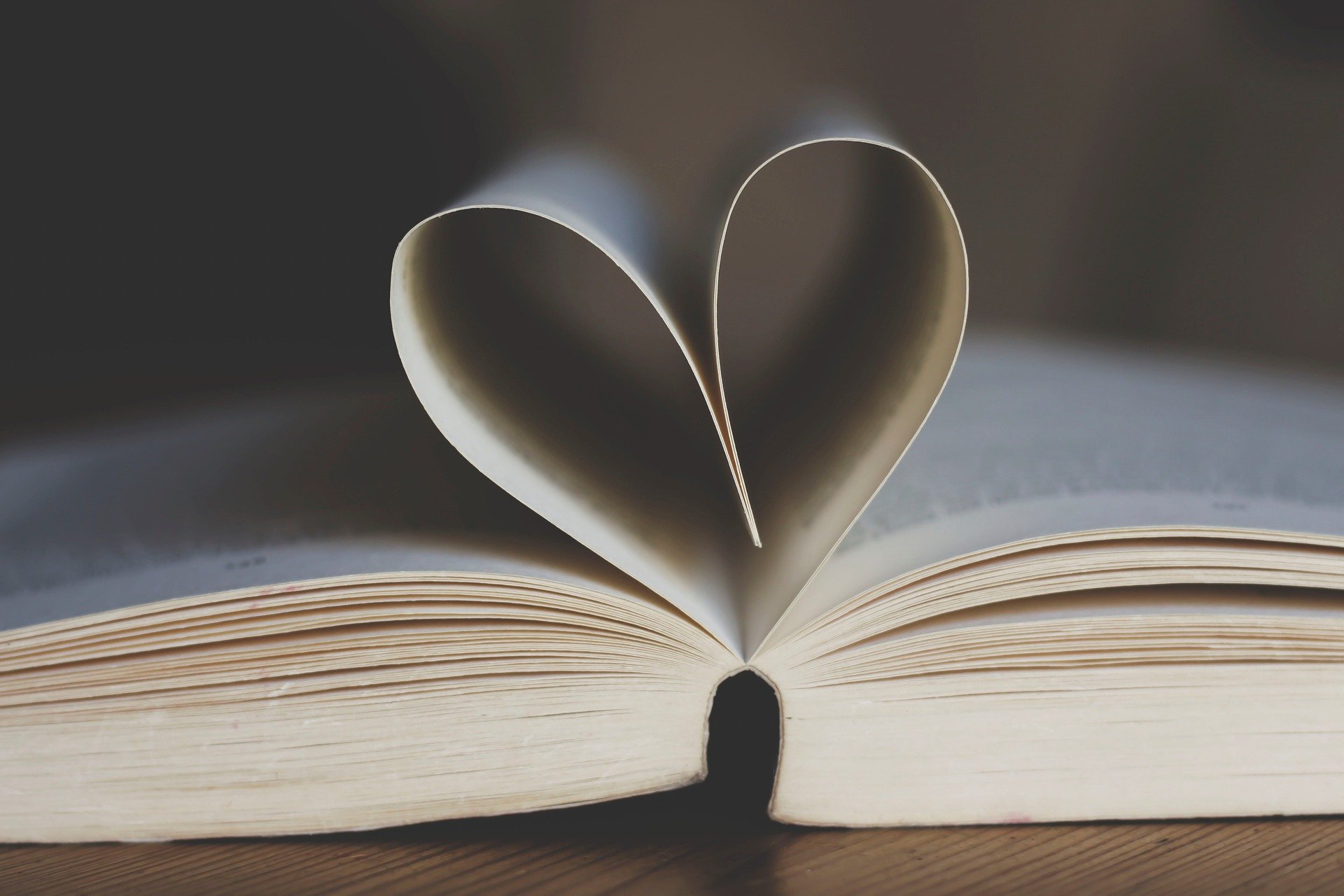
こんなことまで教えるの?
お悩みを聞いて、
お子さんがちょっと混乱しているのかもしれないと感じました。
ママにとっては、
「こんなことまで教えないといけないの?」
と、感じるかもしれません。
講座でも、よくそんな声をお聞きします^^
わたしも、むすこに対して
今でもそう思う日があります。
(まさに昨日も!)
でも・・・
発達凸凹の子どもたちは
教えてもらわないと分からないという特性があります。
” おしっこはトイレでするのが当たり前 ”
こういう概念も自然に学べないのが子どもの生き辛さです。

トイレトレーニングを中断したら
ママやパパがおしっこをする姿を見せてあげましょう。
そして、
「 おしっこでた 」
と、
これがおしっこをするということだよ
ということを教えていきます。
ここで注意点ですが、
ぬいぐるみや絵本で学ぶことは
お子さんの発達に合わせていくことが大切です。
ぬいぐるみや絵本は、
お子さん本人ではありません。
もちろん、
楽しみながら確認していくという意味では
良いですが、どんなに絵本を読んでも
ぬいぐるみを使っても、
それらは実際におしっこができません。
(絵本やぬいぐるみで理解できたらそれはOK!)
年齢が低かったり
発達に遅れがある場合は、
できるかぎりリアルで、実物で、教えていくことが必要です。

やってほしいことを短く伝える
子どもに何かを教えたいと思ったら、
とにかく具体的に教えていきます。
でも、具体的って、説明するということではありません。
例えば、おしっこが出たことを教えてほしいなら
「 ママに、でたって言ってね 」
誰に(名前)、どういえばいいか。
具体的なセリフを短く教えていきます。
それができたら、
「 おしっこでたね 」と、行動を強化していきます。
濡れたら 「 替えて 」もいいかもしれませんが
今後トイレに移行していく場合、
「 出た 」という言葉の方が
トイレでも共通して使用できる言葉です。
お子さんの混乱がひとつ減るかもしれません^^
快と不快は育っているか?
お悩みの中に・・・
布パンツは濡れたら気持ち悪いようだけど、
まだ替えてとは言いません。
と、ありました。
こんな時は、快と不快を教えるチャンスだと思います^^
トイレでできるようになるには、
濡れていると気持ち悪い・・・
替えるとスッキリ気持ちがいい!!
ということを、言葉や表情で教えていきます。
感覚ってひとによって違いますよね。
だからこそ、
お子さんが気持ち悪そうにしてるなとわかったら
「 濡れていると気持ち悪いね 」
「 替えたら、気持ちいいね!」
と、その都度言葉で教えていきましょう。
快(気持ちよい・心地良い)
不快(気持ち悪い・心地悪い)
って、当たり前の感覚ですが
うまく理解していない場合があります。
この感覚は、
人との関わりや自分自身を大切にするということについて
とても重要なスキルになっていきます。

お子さんのトイレトレーニングがすすまないと
とっても焦りますよね。。
でも、ママもわかっているはずです。
ママが焦ると、余計にうまくいきません。。
(わたしもそうでした 汗)
トイレトレーニングを継続する前に
事前にできることがあります。
試してみてくださいね^^